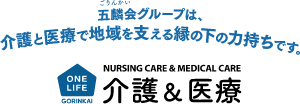そんな私たちであるための5つの理念。

私達は介護と医療を通じて、
-

 患者さんや利用者さんが主体となって
患者さんや利用者さんが主体となって
生活するお手伝いをします。自宅療養の主人公は利用者さん・患者さん本人です。
利用者さん・患者さん・家族・介護者は、介護従事者や医療従事者ではないことがほとんどです。
たとえ利用者さん・患者さんの認知機能が低下していても、機能障害で意思疎通ができなくても、生活の主体は利用者さん・患者さんであるべきだと考えます。私たちが適切だと思うサービスを押しつけてはなりません。
利用者さんや患者さんが自ら選択した方針を尊重した上で、私たちは技術とサービスを提供したいと思います。もちろん、専門家としての適切な助言、提案、場合によっては介護・医療方針決定への上手な誘導も、私たちに必要な技術と考えています。 -

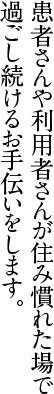 患者さんや利用者さんが住み慣れた場で
患者さんや利用者さんが住み慣れた場で
過ごし続けるお手伝いをします。病院は、本来治療の場であって、生活の場ではありません。
自宅で介護を受ける人、自宅での生活が困難で施設で生活する人。生活の場は様々ですが、病院ではなく、住み慣れた自宅や施設で患者さんや利用者さんが生活し続けるためのお手伝いを、私たちはしたいと思います。 -

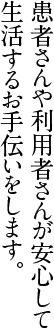 患者さんや利用者さんが安心して
患者さんや利用者さんが安心して
生活するお手伝いをします。入退院を繰り返していた患者さんに訪問診療が介入することで、入院頻度が減っていくケースがあります。重症化する前の介護・医療介入や、ご家族や介護者が見落としがちな徴候に対する、専門家ならではの「気付き」と「問題解決への対応開始」が理由だと思います。加えて「患者さんのホームグラウンドに介護・医療従事者がやってくること」の安心感も、病状安定に寄与していると思います。
「介護・医療従事者がホームに来てくれることで安心する、ほっとする、早めに気づいて対応してくれて助かる」と利用者さん・患者さんが思ってくれているということを、私たちは大切にしていきたいと思います。 -

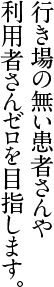 行き場の無い患者さんや
行き場の無い患者さんや
利用者さんゼロを目指します。クリニック開院当時、訪問診療はまだ一般的ではありませんでした。積極的治療を頑張った後に大きな病院から離れることになったものの、住み慣れた地域で次の治療や生活をする場がない「がん難民」と呼ばれる末期がん患者さんが大勢いました。
緩和ケア病棟やホスピスの整備は進んでいますが、十分ではありません。様々な理由で老人ホームに入居できない人や、特養待機者も大勢います。そういう人たちが、「いつもの生活の延長にある、いつかは来てしまう最期を、住み慣れた場で迎えたい」と希望するのであれば、私たちにはそこに至るまでの生活から最期までを支えるお手伝いができます。
病を治して救うことは医療においては最優先の機能ですから、私たちはそのことをしっかりと胸に留め、治し救うことを諦めません。一方で、誤解を恐れずに言いますが、「患者さんがやむなく選択した、死への準備と覚悟」を支えることも、医療の大切な機能の一部だと考えます。緩和医療はその医療機能の一つです。
生まれてきた人数と同じ人数が死を迎えることは辛いことですけれど、抗うことができません。医療業界では「治す医療から、治し支える医療へ」とパラダイムシフトが生じており、私たちは「治し支える」機能で地域のニーズに応えていきたいと思います。 -

 患者さんや利用者さんを
患者さんや利用者さんを
介護する人たちを支えたいと思います。療養の主人公は利用者さんや患者さんです。
一番しんどいのは利用者さんや患者さん、その次にしんどいのは利用者さんや患者さんを介護するご家族、介護者です。
利用者さんや患者さん同様に、ご家族、介護者も不安を抱えながら生活をしています。介護する人がいなければ、利用者さんや患者さんは自宅での生活を継続することが難しくなります。
私たちは利用者さんや患者さんだけでなく、ご家族や介護者も支えたいと思います。
また、患者教育同様、患者家族教育も重要であると考えています。ただしこの教育は、私たち医療従事者が仕事をしやすくするための教育ではなく、「患者さんや利用者さんの利益を第一優先に考えた教育」であるべきだと考えています。